以前福祉制度について軽く書いたのですがもう少し深堀して書いていきたいと思います。
もしもの時に助かるかも知れない制度なのでもし周りの人で該当しそうな人がいれば、是非共有してください。
少しでも悩みが解決できればこの記事を書いた目的も達成されます。

生活困窮者自立支援制度
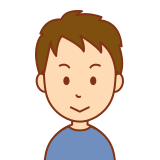
景気が悪くて仕事がなくなってしまって…家賃の支払いもできないし、どうしよう…

大変じゃ、失業保険をもらうにしても期間があるしのぅ…
一緒に使えそうな制度を確認していこうかのぅ。
生活困窮者自立支援制度の概要
1. 生活困窮者が「最後のセーフティネット」である生活保護受給に至る前に、予防的に「第2のセーフティネット」として支援制度が設置されることとなりました。
2.対象者 仕事や生活など、様々な困難により生活に困窮しているかた
資産要件と収入要件が基本的にあります。(自立相談支援事業を除く)
一例として三郷市の要件では下記の通りです。
収入基準額
申請者および申請者と生計を一にしている方の収入合計額が次の収入基準額以下であること。(注)就労収入は総支給額(ただし交通費のみ控除)、自営収入は手取額、年金収入は1か月あたりの総支給額
収入の種類について詳細は別表をご確認ください
- 単身世帯 124,000円
- 2人世帯 175,000円
- 3人世帯 213,000円
- 4人世帯 250,000円
- 5人世帯 288,000円
- 6人世帯 329,000円
資産基準額
申請者および申請者と生計を一にしている方の預貯金合計額が次の資産基準額以下であること。
- 単身世帯 486,000円
- 2人世帯 738,000円
- 3人世帯 942,000円
- 4人世帯以上 1,000,000円
生活困窮者自立支援法の基づいて作られた制度になります。
生活困窮者自立支援法に基づいて作られた制度。
管轄省庁は厚生労働省。
7種類の事業からなっている。
就労準備支援事業の内容
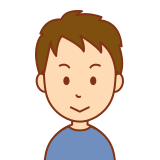
仕事に復帰したいけど、いきなり社会に出るのは不安だな…
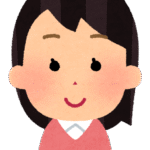
そんな時は就労準備支援事業もあります。
「社会との関わりに不安がある」、「他の人とコミュニケーションがうまくとれない」など、直ちに就労が困難な方に6カ月から1年の間、プログラムにそって、一般就労に向けた基礎能力を養いながら就労に向けた支援や就労機会の提供を行います。
支援の内容
以下のような支援が行われます。
- 日常生活の支援 生活習慣の改善や安定した生活リズムの形成をサポート。
- 社会的スキルの習得 コミュニケーション能力や集団行動への適応など、社会生活に必要な力を育てます。
- 就労体験の提供 実際の職場での体験や、就職活動に必要な知識・技術の習得を支援。
目的
最終的には、利用者が一般就労に移行できるようになることを目指しています。ただし、すぐに就職することだけがゴールではなく、社会的な自立や生活の安定も重視されます。
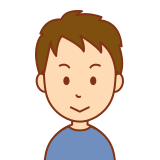
助かったよ。これで少しは自信がついてきた。
でも、体調が悪くて…
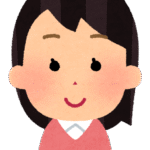
大丈夫ですよ。就労訓練事業もありますよ!
就労訓練事業とは?
- 一般就労がすぐには難しい方に対して、柔軟な働き方を認めながら、段階的に就労に近づける支援を行う事業です。
- 「中間的就労」とも呼ばれ、支援付きの就労体験を通じて、働く力や自信を育てていきます。
対象者
- 働きたい気持ちはあるが、体調や生活リズム、人間関係などの理由で、すぐに一般企業で働くのが難しい方。
- 生活困窮者自立支援制度の利用者で、自立相談支援機関の支援を受けている方が対象です。
支援の内容
- 就労体験の提供:認定された企業や団体が、利用者に合った作業機会を提供。
- 個別支援プログラム:利用者ごとに就労支援計画を作成し、進捗に応じて見直し。
- 支援付き雇用:必要に応じて、雇用契約を結んだ上での支援も可能(雇用型・非雇用型の両方あり)。
- 自立相談支援機関との連携:マッチングや支援計画の作成、定期的なフォローを実施。
実施主体と認定
- 社会福祉法人、NPO法人、企業などが実施主体となり、都道府県や市町村から認定を受けて運営します。
- 認定を受けた事業者には、税制上の優遇措置などもあります。
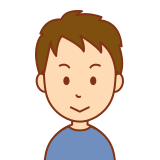
認定を受けてるなら安心だね。
目的
- 利用者が自信を持って社会参加し、最終的には一般就労へ移行することを目指します。
- 就労だけでなく、生活の安定や社会的な自立も重視されます。
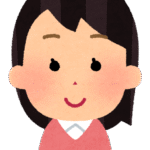
住居確保給付金もあるので併せて確認しましょう。
住居確保給付金の支給とは
「住居確保給付金の支給」は、生活困窮者自立支援制度の一環として、厚生労働省が実施している制度です。主に、住まいを失った方や失うおそれのある方に対して、家賃相当額を一定期間支給することで、生活の安定と就労支援を図ることを目的としています。
支給の概要
- 対象者 離職や廃業などにより住居を失った方、または失うおそれの高い方で、以下の条件を満たす方:
- 主たる生計維持者である
- 世帯収入や資産が一定基準以下
- ハローワーク等に求職申込を行い、誠実に就職活動をしている
- 支給内容 家賃相当額を原則3か月間支給(最大9か月まで延長可能)。支給額は地域や世帯人数により異なり、生活保護制度の住宅扶助額が上限となります。
- 支給方法 給付金は、申請者本人ではなく、賃貸人や不動産仲介業者の口座に自治体から直接振り込まれます。
東京の3等級の地域で一人暮らしなら約4万円が上限です。
転居費用の補助もあり
- 家計改善のために家賃の安い住宅へ転居する必要がある場合、転居費用の補助も受けられることがあります。
- 敷金や礼金などの初期費用の一部が対象ですが、補助対象外の経費もあるため、詳細は自治体に確認が必要です。
注意点と申請の流れ
- 申請先:お住まいの地域の自立相談支援機関
- 必要書類:本人確認書類、収入・資産状況の証明、求職活動の記録など
- 求職活動の要件:月2回以上の職業相談、週1回以上の応募など、具体的な活動が求められます4
この制度は、単なる家賃補助ではなく、住まいの安定を通じて就労や生活再建を支援する仕組みです。
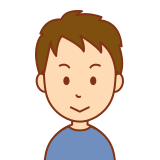
これは凄くいい制度ですね。
貯金もあとわずかで家賃が支払えないところだったので助かりました。
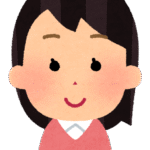
学さんにぜひ利用してほしい制度があります。家計を改善する支援がございます。
一緒に黒字家計を目指しましょう。
家計改善支援事業とは?
- 家計の状況を「見える化」し、根本的な課題を把握したうえで、相談者が自分自身で家計を管理できるようになることを目指す支援です。
- 支援員が寄り添いながら、家計の再生に向けた計画づくりや助言を行います。
主な支援内容
- 家計アセスメント:家計表やキャッシュフロー表を使って、収支の状況を整理。
- 支援計画の作成:相談者の状況に応じた家計改善プランを立案。
- 相談支援:生活費の使い方や支出の見直しについて助言。
- 関係機関との連携:必要に応じて、貸付制度のあっせんや債務整理の支援も行います。
- 金銭教育:家計管理の基本や消費者被害の防止に関する情報提供も含まれます。
対象となる方
- 生活費のやりくりに困っている方
- 滞納(家賃・公共料金など)がある方
- 借金や多重債務を抱えている方
- 家計の立て直しに不安を感じている方
支援の進め方(例)
- 相談受付・アセスメント:家計状況や課題を把握
- 支援計画の策定:目標と改善方針を設定
- 支援の実施・モニタリング:定期的に面談し、進捗を確認
- 評価・終了:目標達成後、支援を終了または次の段階へ
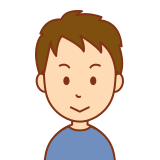
ほかにも種類があったよね?
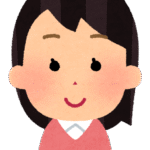
一時生活支援事業などもございますよ。
一時生活支援事業とは?
- 住居を持たない方や、ネットカフェ・知人宅などで寝泊まりしているなどの不安定な住居形態にある方に対して、一定期間、宿泊場所や食事、衣類などを提供します。
- 原則として3か月以内の支援期間ですが、状況に応じて延長されることもあります。
対象となる方
- 現在、住居がない、または住居を失うおそれがある生活困窮者
- 所得や資産が一定基準以下であること
- 地域社会から孤立している、または支援が届きにくい状態にある方
支援の内容
- 宿泊場所の提供(簡易宿泊所、シェルターなど)
- 食事の提供(1日3食など)
- 衣類や日用品の提供
- 生活相談・就労支援:退所後の生活再建に向けた支援も行われます
- 訪問支援:路上生活や不安定な居住状態にある方へのアウトリーチも含まれます
他の支援との連携
- 自立相談支援事業と密接に連携し、利用者の状況に応じた支援計画を立てます。
- 必要に応じて、就労準備支援事業や住居確保給付金など、他の支援制度とも組み合わせて支援が行われます
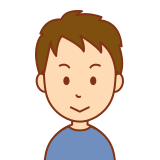
住む場所がないと社会復帰が難しいからね。
生活困窮世帯の子どもの学習・生活支援事業とは?
🎓 事業の目的
この事業は、「貧困の連鎖」を断ち切ることを目的に、生活困窮世帯の子どもたちに対して、学習支援や生活支援を通じて、将来の自立を後押しするものです。
📚 主な支援内容
- 学習支援 学校の授業の補習や宿題のサポート、学習習慣の定着、高校進学支援など。
- 生活支援 日常生活の習慣づけ、社会性の育成、仲間との交流の場(居場所づくり)など。
- 進路・就労支援 高校中退防止、進学や就職に関する相談・助言、職業体験の機会提供など。
- 保護者への支援 子育てや教育に関する相談、家庭訪問による支援、関係機関との連携。
🧑🤝🧑 支援の特徴
- 子どもと保護者の双方を支援 子どもだけでなく、保護者にも寄り添い、家庭全体の安定を目指します。
- 地域資源の活用 学習支援ボランティア、教員OB、地域の子ども食堂、企業などと連携。
- 自立相談支援事業との連携 必要に応じて、他の支援制度と組み合わせて包括的に支援します。
🏫 対象となる子どもたち
- 生活保護世帯や就学援助世帯など、経済的に困難な状況にある家庭の子ども
- 小学生から高校生まで、または高校中退者や中学卒業後未進学者なども含まれる場合があります(自治体により異なります)
この事業は、単なる「学習塾」ではなく、子どもたちの未来を支えるための多面的な支援です。
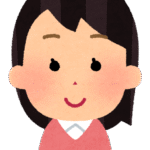
以上が生活困窮者自立支援制度の内容です。
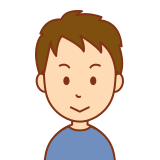
沢山の種類があってとても心強いね。
特に最後の子供たちの支援は素晴らしくて感無量だね。
貧困の連鎖を断ち切る。僕の心にも深くささったよ。
終わりに
経済的に困窮することは誰にでもあります。
特に昨今では子供の貧困が取り上げられており、満足なご飯も食べれない子供たちも一定数存在します。
よく貧困は自己責任といわれていますが、貧困世帯とその他の世帯を比較した際に教育機会や体験格差などを通じて、社会に出る前から圧倒的に不利な状況があります。
そのような状況から貧困の連鎖はつないでいかれます。いかにこの負の連鎖を止めるか、是非皆さんには議論していただきたいです。
【広告】
養育費用の保証をしてくれる民間会社があるので要チェックです。
養育費が支払われなくなる可能性が現代の日本社会では多いのでいざという時に入っとくことをお勧めします
初回契約時に養育費の一月分の費用と月額養育費の3%で加入することができます。
もし養育費用が5万円とすると…
最大5×36=180万円まで補償されます。

自分の子供を守るのは自分自身なのじゃ
是非加入審査の申し込みだけでもしてみて下さい。

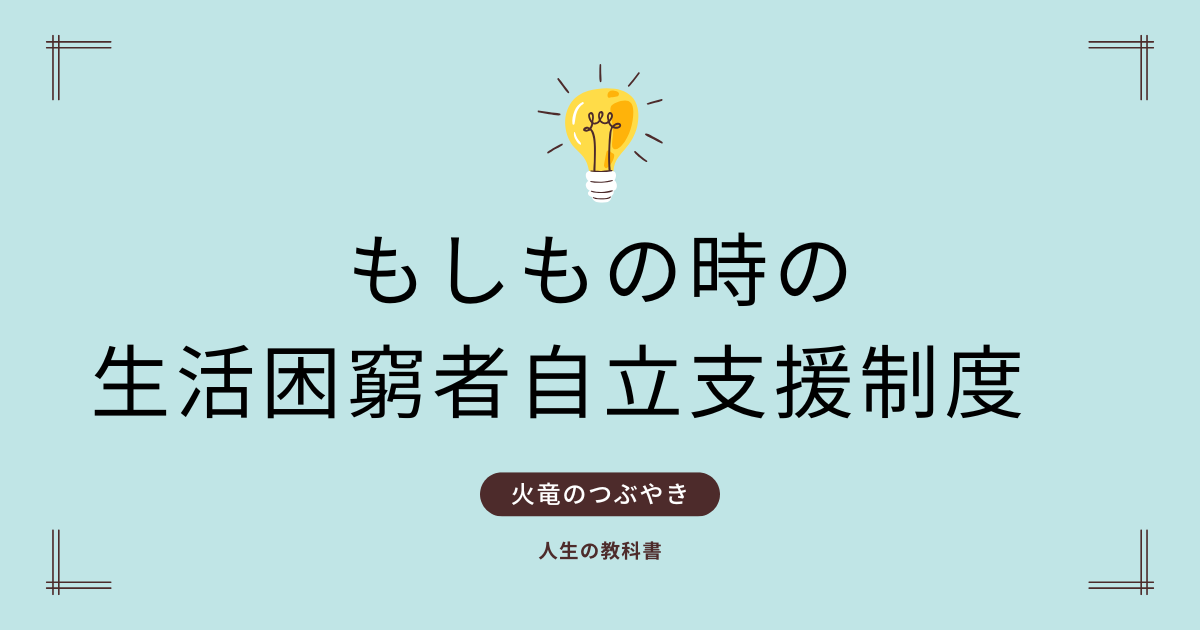

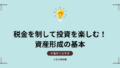
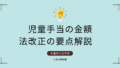
コメント