
※本サイトで紹介している商品・サービス等の外部リンクはプロモーションが含まれています。
病院に行きたいけど医療費払えない…
そのように不安を考えている人は少なくありません。
経済的にあきらめる前にこの記事を見て公的な制度を活用できないかを考えてみてください。

この記事を見ると救済制度がわかる。
医療費が払えないときの解決策:支援制度一覧
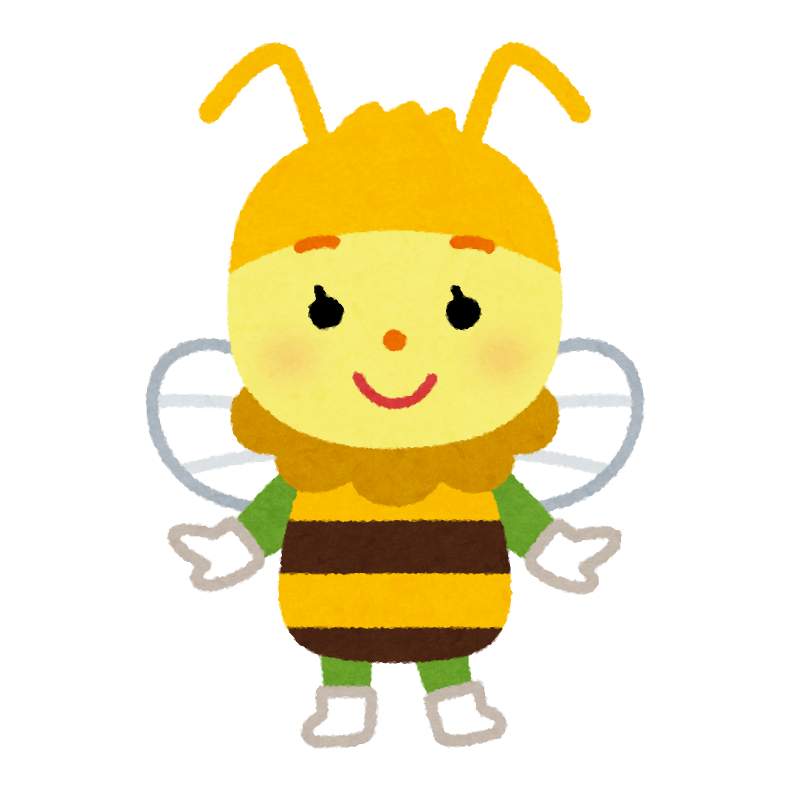
お金がなくて病院にいけないぴ

日本には色々な制度があるんだよ。例えば生活保護もそのうちの一つだね
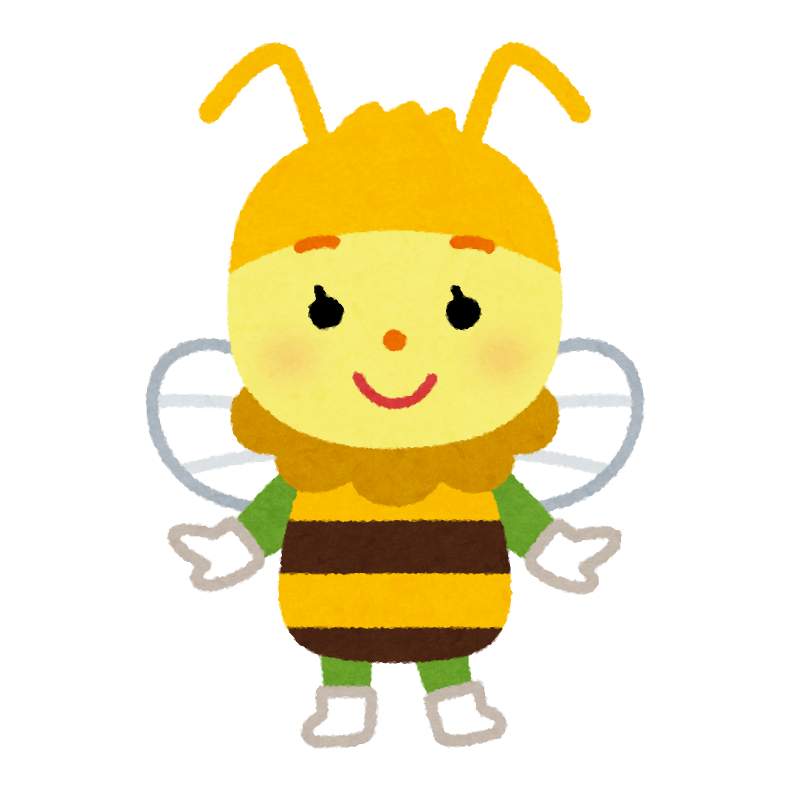
それは…他にもあるぴ?

他にもあるよ。一緒に見ていこう
- 高額療養費制度
- 自立支援医療制度
- 無料低額診療事業

高額療養費制度とは?
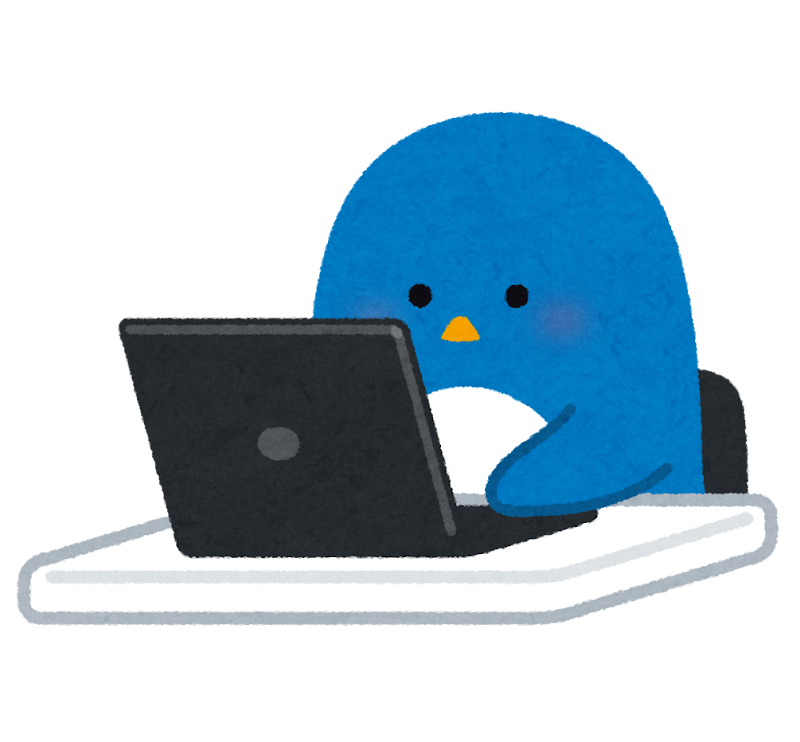
高額療養費制度は自己負担の上限が決まってるんだぜ
高額療養費制度は医療費が高額になった際に負担を軽減するための制度です。
月額の上限が収入で決まります。以下にまとめたのでご覧ください。
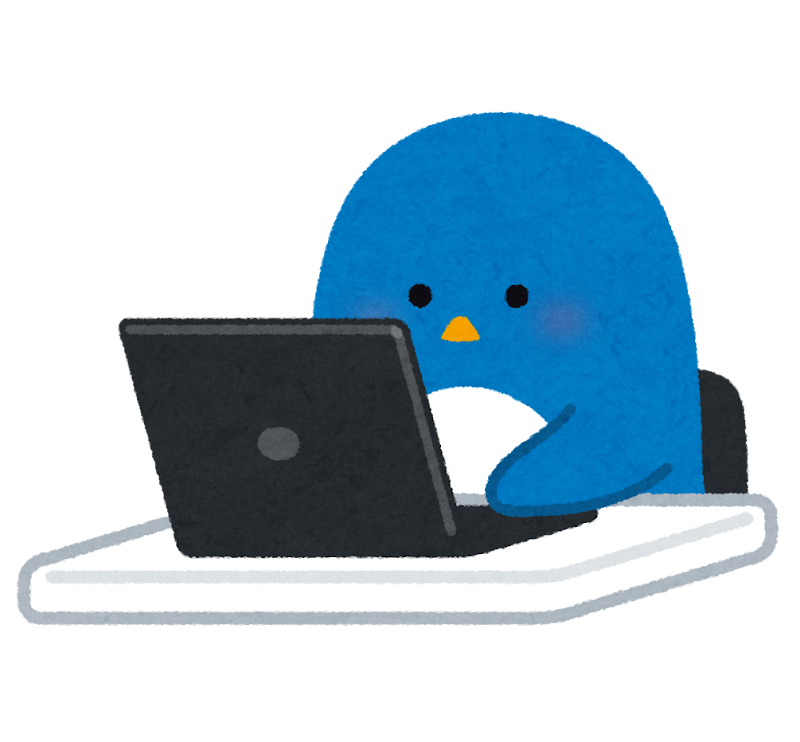
超えた分は後から戻ってくるぜ
高額療養費制度:自己負担額早見表
(作者:火竜のつぶやき)
70歳以上の場合
| 所得区分 | 月々限度額の目安 | 式の概要 |
|---|---|---|
| 現役並み(年収約1,160万円~) | ≈25.3万円+(医療費-842,000円)×1% | 例:医療費100万円 → 自己71,330円 |
| 現役並みⅡ(770~1,160万円) | ≈16.7万円+(医療費-558,000円)×1% | |
| 現役並みⅠ(370~770万円) | ≈8.01万円+(医療費-267,000円)×1% | |
| 一般(156~370万円) | 18,000円 | |
| 住民税非課税Ⅱ | 8,000円 | |
| 住民税非課税Ⅰ | 15,000円 |
69歳以下の場合
| 所得区分 | 月々限度額の目安 |
|---|---|
| ア:1,160万円~ | ≈25.3万円+(医療費-842,000円)×1% |
| イ:770~1,160万円 | ≈16.7万円+(医療費-558,000円)×1% |
| ウ:370~770万円 | ≈8.01万円+(医療費-267,000円)×1% |
| エ:~370万円 | 57,600円 |
| オ:住民税非課税 | 35,400円 |
具体例(70歳以上・現役並みⅠの場合)
- 医療費:100万円
- 窓口負担(3割):300,000円
- 限度額算出:80,100円+(1,000,000−267,000)×1% ≒ 87,430円
- → 高額療養費支給:212,570円
- → 実質自己負担:87,430円
補足ポイント
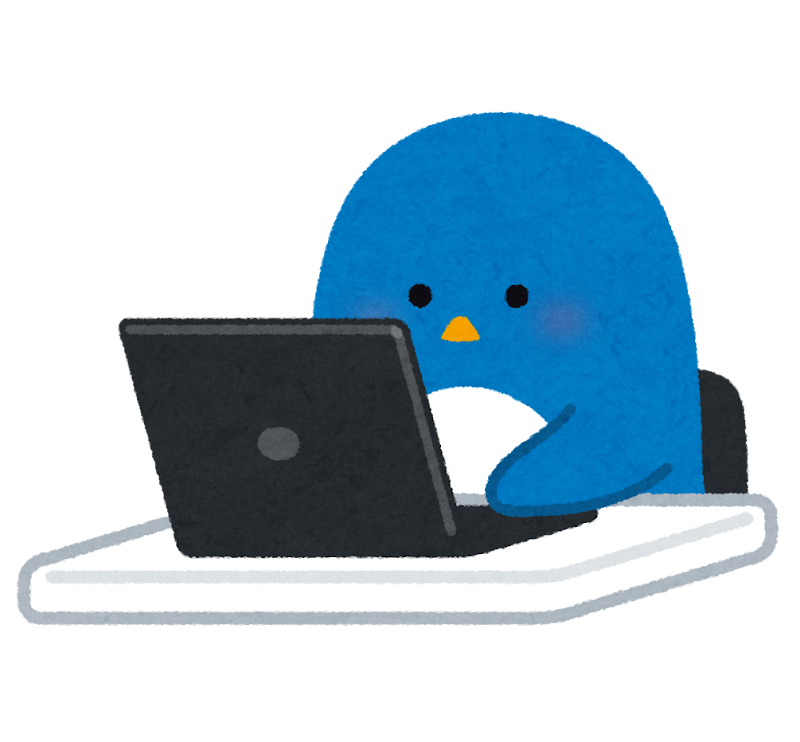
「世帯合算」(同月・同一保険加入家族)合算できるぜ
「多数回該当」(12ヶ月内3回以上上限に達した場合の軽減額)減額金額が増えるぜ
「限度額適用認定証」役所に申請すると窓口負担を抑えれるぜ
自立支援医療制度とは?

自立支援医療制度は医療費を公費で一部負担してくれる制度です。
分類と対象
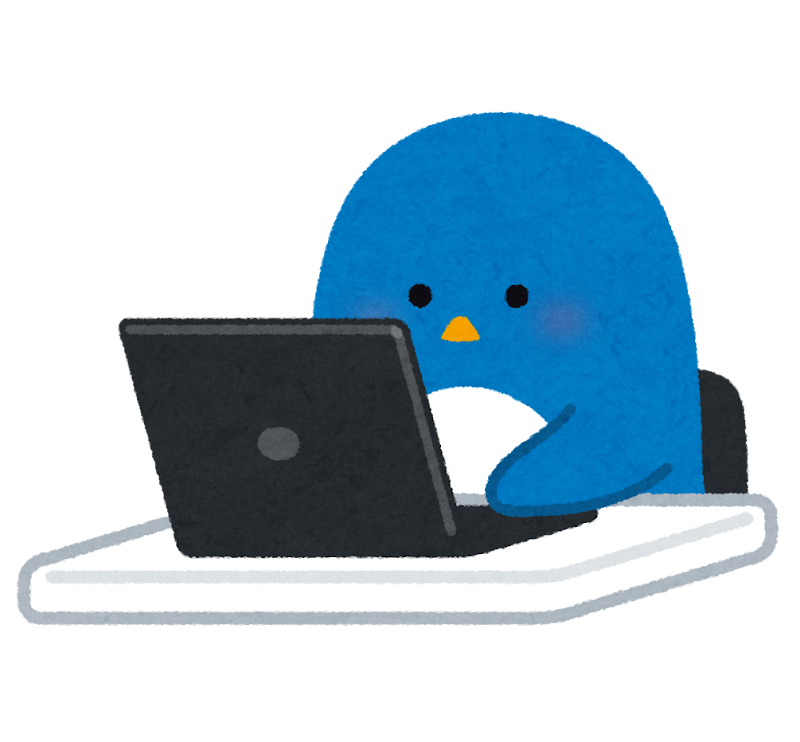
医者の診断書が必要だぜ
- 精神通院医療: 統合失調症やうつ病などの精神疾患で通院が必要な方。
- 更生医療: 身体障害者の社会復帰を支援するための手術など。
- 育成医療: 障害児の健全な発育を支える医療。
利用者負担
自己負担は所得に応じて1割。ただし、月ごとの上限額が設定されています。
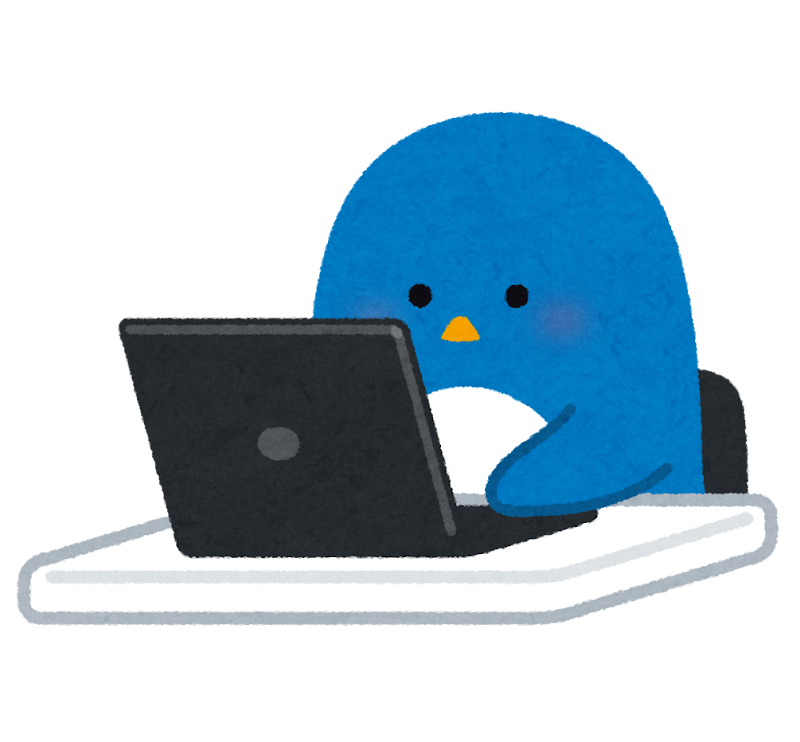
非課税なら上限金額が2500円だったぜ
実際利用したことがありますが、住民税非課税世帯なら2500円でいけました。
確かその上の区分で5000円ぐらいでした。
国民健康保険の時一割負担も完全に無料でした。
※自治体で違う可能性もありますので要確認。
申請方法
お住まいの市区町村の障害福祉窓口で申請が可能。医師の意見書などが必要です。

無料定額診療事業制度とは?

料定額診療事業制度は、経済的に厳しい状況にある人々が必要な医療を受けられるよう、無料または低額な料金で診療を提供する制度です。
対象者
- 低所得者、要保護者
- ホームレス、DV被害者、人身取引被害者など
- 国籍や医療保険加入の有無に関わらず、生計が困難な人
注意点
- 原則として支援は一時的であり、最大でも無料診療で1~3か月間の適用
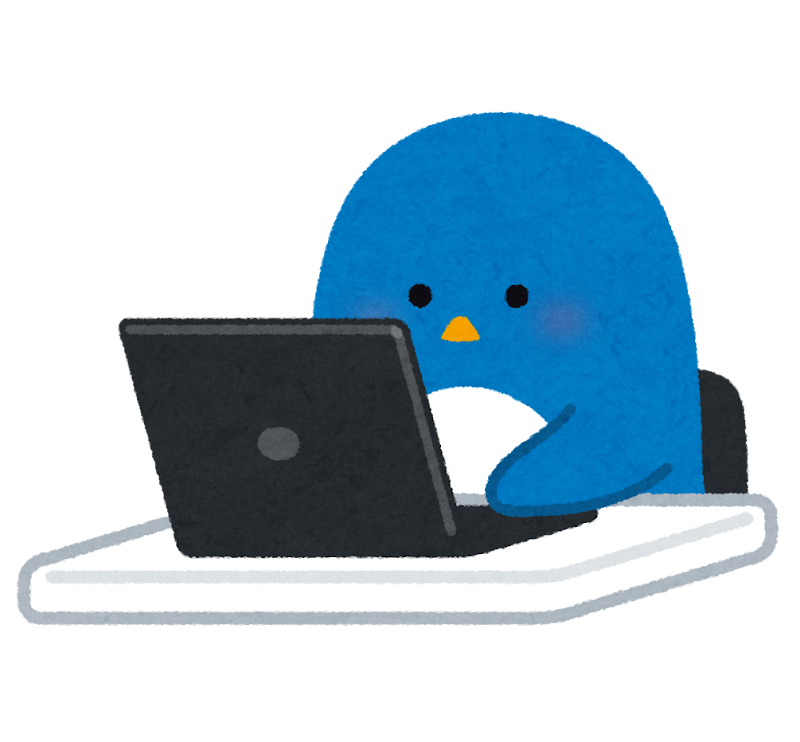
あくまでも一時的に使う制度だな
利用方法
医療機関に相談する この制度を実施している病院や診療所に直接相談します。ここで自分の状況を説明し、支援が可能かどうか確認します。
申請手続き 面談でのヒアリング後、収入証明書や保険証(なくても相談可能)などの必要書類を準備し、申請します。
審査結果の通知 提出書類をもとに審査が行われ、制度適用の可否が通知されます。適用される場合は無料または低額診療券が交付されます。
診察を受ける 診察券を使用し、実施医療機関で診療を受けます。窓口での支払いは無料または低額になります。
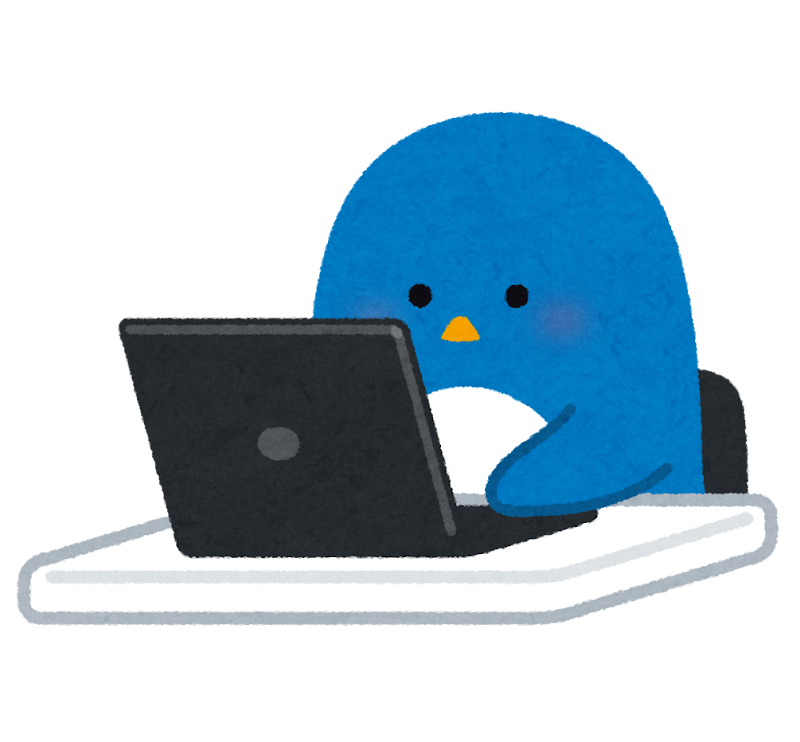
制度に関する相談や手続きは、社会福祉協議会や福祉事務所でも相談できるぜ
まとめ
医療費の支払いに困ったときは一人で抱えこまないで下さね。
今回ご紹介したような多くの支援制度が存在しており、これらを活用することで経済的負担を軽減することができます。
まずは、役所や福祉事務所、医療機関へ相談してみましょう。一歩踏み出すことで、安心できる未来への扉が広がります。すべての人が必要な医療を受けられる社会を目指して、一緒に情報を共有し、活用していきましょう。
火竜のつぶやきからのまとめでした。読んでいただき、ありがとうございました!✨
【PR】
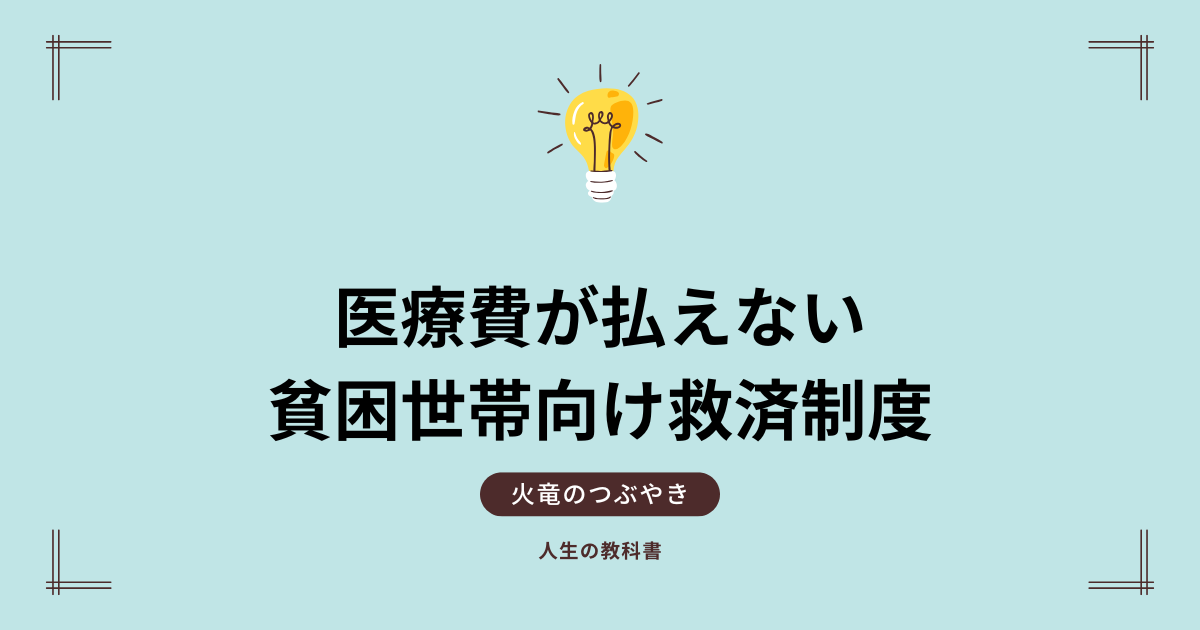
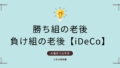

コメント